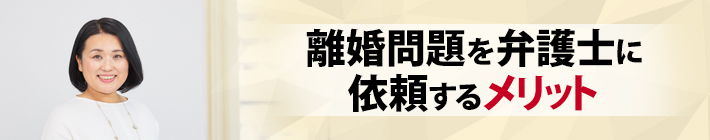子どもの引き渡し【監護者指定について弁護士が解説】
夫(妻)に子どもを連れ去られた場合にはどうすればいいのか?
夫婦関係が悪化して夫婦の一方が家を出た際に、未成年のお子さんについてどちらが面倒を見るかで紛争が生じてしまう場合があります。
ご自身が子どもの面倒を見たい場合には、家庭裁判所に「監護者指定、子の引渡し審判」「審判前の保全処分」という申立てをすることを検討しましょう。
監護者指定、子の引渡し審判とは
「監護者指定審判」とは、夫婦が離婚するまでの間、未成年のお子さんの面倒を夫婦どちらが見るべきか、家庭裁判所に判断を求める手続きです。
「子の引渡し審判」とは、未成年のお子さんを自分の方に引き渡すべきである旨、家庭裁判所に判断を求める手続きです。
監護者に指定されても、子どもが自分のもとに来ないと実際上の意味がないので、監護者指定と子の引渡し審判はセットで申し立てることが一般的です。
審判前の保全処分とは
「審判前の保全処分」とは、現在のお子さんの監護状況に問題がある場合に、「監護者指定、子の引渡し審判」の申立ての判断が出て確定するまでの間に、「仮に」お子さんの面倒を自分が見る、「仮に」お子さんを自分の方に引き渡すように裁判所に判断を求める手続きです。
裁判所が、監護者指定、子の引き渡し審判において、「お子さんをどちらの親が面倒を見るのが良いか」を判断するには、現在のお子さんの養育状況や夫婦の話を聞く等、様々な調査をする必要があります。この調査は半年~1年程度かかることも珍しくなく、時間がかかってしまいます。もし、お子さんがその間に、夫(妻)から暴力を受けていたり、他方の親の悪口をたくさん聞かされていたら、お子さんの健全な成長は深く損なわれてしまいます。
そのため、手遅れになる前に、仮にでもいいので、早期にお子さんの監護者に指定されて、引渡しを受けるために行うのが、審判前の保全処分という手続きです。
この通り、審判前の保全処分の最大のメリットは、迅速な判断を得られる点です。裁判所も審判前の保全処分が申し立てられた場合は、事案によって優先度を柔軟に検討しています。裁判所が迅速に審理する必要性が高いと判断した場合は、申立てから1~2週間で初回期日が設定されることもあります。裁判所の審判まで2~3か月程度で終了することもあり、監護者指定、子の引渡しに比べて、かなり早期に判断が出ます。経験豊富な弁護士であれば、審判前の保全処分を申し立てた方が良いか、アドバイスが可能ですので、早めに弁護士にご相談されるといいでしょう。
即時抗告をされても執行停止効がないので、強制執行ができる
審判前の保全処分のメリットは他にもあります。保全処分ではない、監護者指定、子の引渡し審判では、これらが認められても、相手がお子さんの引渡しをさらに争い、高等裁判所に再度審理を求める場合(即時抗告といいます)には、審判が確定せず、お子さんの引渡しの強制執行ができません。
しかし、「審判前の保全処分」は、即時抗告されても執行停止の効力が無いので(家事事件手続法111条1項参照)、保全処分の結果に基づき、お子さんの引渡しの強制執行をすることができます。この意味でも、早期のお子さんの引渡しを求めることが出来ます。
子の監護者指定・引渡し審判の流れ
子の監護者指定、引渡し審判は、申立書に記載する事項が極めて専門的で難しいです。また、速やかな申立てが重要です。
そのため、すぐに弁護士に相談することを強くお勧めします。
とびら法律事務所で実際に扱った監護者指定・子の引渡し審判、審判前の保全処分事件のタイムスケジュールです(守秘義務の都合上、多少事実を修正しています)。他のケースでもこのスケジュールで進むわけではありませんのでご注意ください。
①ご相談、その日にご依頼、集めていただく資料をご説明
②お打合せ(ご依頼から(以下同じ)3日後。)
・これまでのお子さんの監護状況や、引渡しを受けた後の監護計画などについて「子の監護に関する陳述書」という書類を作成することが多いです。
③子の監護者指定、引渡し審判申立書の裁判所への提出(10日後)
④相手方の答弁書提出(3週間後)
⑤初回審判期日(1か月後)
※ポイント
審判前の保全処分を申し立てていないと、初回期日がもっと先になってしまいます。
期日では実際に裁判所に出向き、申立てをした経緯などを話した上で、家庭裁判所調査官による調査の内容や日程などを決めます。
⑥家庭裁判所調査官による父母の面談(2か月後)
⑦家庭裁判所調査官によるお子さんの様子の調査(2.5カ月後)
⑧家庭裁判所調査官による調査報告書の完成(3.5か月後)
※ポイント
調査報告書は、調査によって判明した事実と、調査を経た上での家庭裁判所調査官の意見が書かれています。裁判官はこの調査報告書の結果を非常に強く尊重しますので、調査報告書の内容が極めて重要になります。
⑨裁判官による審判(判決のようなものです)(5か月後)
⑩お子さんの引渡し強制執行(6か月後)
監護者指定を有利に進めるためのポイント(考慮要素を理解する)
子の監護者指定、引渡し審判が認められるための考慮要素としては、一例ですが、以下の事情が挙げられます。
・主たる監護者(父母の別居までの間に主に面倒を見ていた者は誰か)
・現在の監護の継続性(現在の環境をできる限り変えてはいけないとの考え方)
・監護状況の良し悪し
・監護補助者の存在
・違法な監護の開始の有無
・別居中の面会交流の状況(積極的に面会交流を実施しているかどうか)
上記の事情を総合的に考慮して、裁判所は、父母のどちらがお子さんの面倒を見るのがお子さんの健全な成長により良いのかを判断します。
そのため、上記のポイントを意識しながら、子の監護者指定、引渡し審判を申し立てることが大切です。
説得的な申立書を作成し、証拠を提出する
上記の考慮要素を意識しながら、裁判所に説得的に主張をし、また適切な証拠を提出することが必要です。どんなに自分の方が子どもにとって良い親だとしても、裁判所は証拠の有無をとても重視します。ここでいう証拠の有無というのは、物的な証拠だけでなく、状況証拠や第三者の証言なども含みます。
経験豊富な弁護士は、相談者の方から事情を丁寧に聞き出し、説得的な主張をするほか、主張を裏付ける証拠の集め方についてもアドバイスをします。
困ったときには、ぜひ経験豊富な弁護士に相談をしてください。
解決事例
とびら法律事務所の監護者指定・子の引渡しプラン
とびら法律事務所では、監護者指定、子の引渡し事件を多数取り扱った経験があり、監護者指定・子の引渡しプランをご用意しております。
>>詳しくはこちら
監護者指定、子の引渡し審判を申し立てるべきか、どのような進め方が良いかは、弁護士に直接ご相談の上、弁護士と一緒にご検討ください。
とびら法律事務所の弁護士は、ご相談者様のご意向を伺ったうえで、ご相談者様に最適なアドバイスを心がけております。